▼つづき2009/09/24 08:04 (C) ぼくのニワトリは空を飛ぶー菅野芳秀のブログ
▼ダーチャ…そして、クラインガルテン ダーチャについて米原マリの本に詳しく書かれていますね。 野菜作り、プラス、週末を過ごす簡易別荘、とでもいうような、施設みたいですね。 ドイツには、クラインガルテンというものがあります。私も借りていますが、町から1区画50平方mぐらいの広さを借り受けます。これが50とか100とか並んでいます。そこに、小さな物置小屋や、ガルテンハウスという、小さな家を建てて(寝泊まりは一応禁じられている)バーベキューパーティーをしたり、週末の余暇を楽しんだりするんです。 私は、単に菜園として使っているだけですが、ほとんど夕方毎日、そこへ来て暗くなるまでビールを飲んで、バーベキューをしている家族もあるんですよ。 原則、庭のない家庭に貸し出されていますから、庭代わり、文字通り、クラインガルテン小さな庭、なんですね。 収穫も結構大したもので、ロシア人が飢餓から救われたっていうのもあながち誇張とも思えませんね。生ごみをたい肥にしたり、野菜を育てたり、自然と生活がなじみ合うには素晴らしいチャンスだと思います。 因みに、私の両親は東京の大田区に住んでいて、区民農園を予約しようとしたのですが、空席待ちに3年はかかるんだそうで、あきらめざるを得ませんでした。都会の人々こそ、こうした機会が必要なんでしょうけど、土地がなんて言っても高いですからね。 行政がこうしたことに本腰を入れなければできないことですが、そのためには、行政を動かすだけの市民の力と強い動機がなければなりません。その力や動機が、日本には見られないように私は思っています。お上ですからね。行政は。 2009/09/25 17:43:くみ
▼農村の食文化!ツノマキ この前の連休に、種子島に帰ったとき、島農村伝統の「ツノマキ」(粽の一種)をご馳走になった。今、農家の主婦でもあまり作らなくなったという。昭和30年代には、このマキに黒砂糖をまぶしてよく食べた。 餅米、灰汁、水、ダチク(竹の一種)の葉、ミチシバが原材料である。写真の通り、一人一個といったところであるが、菅野先輩のように体の大きい人は、一回に2〜3個食べる人もいる。普通、一人一個食べれば十分である。 中国伝来ということであり、また兵糧食とも聞く。このような農村の伝統的お菓子(おやつ)?の復活も農村再生に繋がればと思う次第です。 先輩、山さくらさん、そして農村再生をめざす皆さん、一度食べてみませんか。更に農村食文化への関心が高まりますよ。 2009/09/26 11:48:種子原人
▼ベランダにアブラナを蒔いて秋日和に、ベランダのプランターと植木鉢に菜種を蒔きました。
これだけで、気分がすっきりして。 この鉢はこの前まで落花生を植えていたところです。 たいして碌な堆肥も作れないベランダ。アブラナから油粕までいけるかしら?そんな想像も楽しんでます。 楽しくなけりゃ、そして自分の暮らしを作らなけりゃ。 そんな思いは、小さな、小さな植木鉢の中にもあります。 ・・・多少、消化不良になる時もありますが。 2009/09/27 08:26:文庫 番:URL
▼よくわからないことばっかり〜! ただ、菅野さんの生き方、考え方、すっごくかっこいいですねって思います。それで生きていけたら、最高だわ〜って、私は思います。 それに、黄金のさざ波って凄いですね。800ヘクタールだから広いんですよね。雪のときもステキ、早苗のときもステキ、黄金のさざ波も見ごたえありますね。・・・でも、写真だけじゃあ〜・・ね!? 私の知り合い(稲作農家25ヘクタール)が、この「黄金のさざ波を夢みることで一年頑張れるんだよ」って言っていました。 それだけ作っていても、生活は楽じゃないんですって、他の仕事もしていますよ。ほんで奥さんは、他のお仕事していますよ。 だからね、菅野さんのように家族みんなで、同じ気持ちで生きて行けるって最高なんじゃないですか・・・・ねっ! ダーチャって、よく聞くけどわからない。 種子原人さんの写真のツノマキは甘くて美味しそうですね。食べてみたいで〜す。でも想像できない。私は讃岐うどん大を食べるから、ツノマキ2個食べられるかもですね? 以前教えていただいた、アクマキも鹿児島の伯母の手作りなんですって。もう何十年も名前知らずに戴いていました。 実家の母は、チマキって思っていたんですって・・・! この秋は、山の栗とポンタン(ボンタン?わかんないです)飴を山ほど送ってもらいました。もう何十年も同じ物を送ってくるんですよ。春と秋にね。 たぶん生きている間(送れる間)送ってくるんですよね!「もう大変だからいいですよ」って言ってもね。・・・・だって90歳過ぎて一人暮らしなんですよ。いのししと知恵比べしながら、田畑と山の仕事頑張っているんですよ。仙人みたいでしょう? 【写真】→讃岐の田んぼの畦です。大きくして見てください。段々の田んぼなので畦が広いです。 10月10日に我が家は餅米を刈ります→10㌃弱です。 10㌃は1反のことだって、わかっていますからね。 2009/09/27 14:33:山さくら:URL
▼ボンタン飴(文旦飴)とは先輩、またまたこのコメント欄をお借りします。
ボンタン(文旦)飴とは、鹿児島の代表的な飴菓子で、キャラメルに似た食感の飴菓子です。 ボンタン(大きな蜜柑、夏ミカンよりも一回り大きい)の果汁、水飴、もち米を原料とするものです。お年寄りや歯の悪い人は、食べづらいかもしれません。入れ歯にくっつく、銀の詰歯が剥がれる・・・ しかし、歯の丈夫な人や若い人は、美味しいと感じるのではないでしょうか。今、全国のコンビニなどで売られていると聞きます。長井では販売されていませんか。 2009/09/28 13:04:種子原人
▼種子原人さんへ! ボンタン(文旦)ありがとうございました。 讃岐のスーパーでも売られているんですよ。これは、鹿児島にしかないって思っていたので、見つけた時はすっごく懐かしくて嬉しかったです。でも、みんなどこでも食べられるんだって思ったら、少し寂しかったですけどね。 菅野さんの、難しい百姓の、いやいや人間としてステキな格好いい生き方の内容のブログに、ちょっと楽しい遊びの話(楽しいのは私だけかな?)で、ごめんなさいです。 今度、私たちの宗吉瓦窯会の仲間で芋煮会をすることになりました。私は、もちろん生まれて初めてです。 昨年、深夜便で菅野さんのお話の中に出てきてから、ず〜っと{いつかやりたい→イヤいつかやるんだ}って思っていました。鹿児島にはありますか? 無いですよね。それに、芋って言ったら、サツマイモですよね。讃岐もそうです。「芋掘り」って言うけど「サツマイモ掘り」って言わないですよね。他の芋は、ジャガイモとかサトイモとかヤマイモってきちんと名前で呼びます。 それで、私は「牛肉とお醤油ですよ。芋はサトイモですよ」って言ったんだけど、私以外のみんなは、芋はサトイモだけど、鶏肉と醤油がいいんですって・・!食べて美味しかったんだそうです。私は、それも食べたこと無いから従うしかないですね。 ほんで、古代米でお餅つきもします。黒米と緑米を使ってね。 さらに、野焼きもします。(みんなが作って乾燥できている弥生土器を焼きます) 10月14日(水)朝からです。「野焼きを見たい人・古代米のお餅を食べたい人・芋煮会に集まれ〜!」ですよ! 種子原人さん、いかがですか?・・・菅野さんは稲刈りでお忙しいですからね。本当は芋煮会のご指導していただきたいのですけどね!そんなこと言ったら「アホか!この忙しいのに、ほんまにもう、何考えとんじゃ〜!」って、怒鳴られそうでしょう。・・・だから、内緒ナイショです。ここ見ませんように! 写真は、スマ刈りです。コンバインで稲刈りをする前に、田んぼの角を4箇所このように手で鎌を持って一株づつ刈ります。 コンバインが、入って作業しやすいようにね。つい、最近聞いた話ですが、人に頼んでしてもらうと、一角→500円なんですって!・・・一枚の田んぼは4角あるから2000円ですね。 だから、一枚の田んぼの稲刈りしていただくのに、どんなに小さい田んぼでも、それはプラスされるんですよ。 2009/09/29 07:45:山さくら:URL
▼山さくらさんへ!芋煮会なるものは、鹿児島市周辺では聞いたことがありません。河原での芋煮会は度々聞くのですが、鹿児島市周辺以外ではどうかわかりません。今年は、野外でのバーベキュー大会もあまり聞きません。つまり、桜島の降灰の影響かと思われます。やはり、桜島噴火口の蓋は必要です。ここ鹿児島は、サツマイモ、ジャガイモ、山芋、里芋と「芋」の豊富な地域ですが、野外で食べるにはやはり気象条件に左右されます。
なお、故郷=種子島では、宝満神社の氏子集団による赤米(古代米)を栽培し、豊作を祝う秋祭りもあります(さほど美味しくはないとのこと)。 あまり、食べる話ばかりしているとお腹がすいてきました。寝ます。山さくらさん、先輩、お休みなさい。芋煮会には、夢の中で出席します。 2009/09/30 00:11:種子原人
▼ブログの主旨を乱して・乱して!ごめんなさい! 菅野さんへ! → 私、いつも道草(寄り道)で、ここの欄をいっぱい使ってごめんなさいです。 ほんで自分のことばっかりでスイマセンです。 文庫番さん、お久し振りですね。なんかお名前を拝見してホッとしました。落花生って育てて、食べられるようにするまでが大変なんですが、面白いんですよね。地面の上にある茎が地面に潜って実が成るんですよね。 随分前に作ったことがあって、すっごく楽しかったし発見が一杯あったのを思い出しました。 アブラナって今頃種まきするんですね。私、菜花は育てたことあるけど種まきしたこと無いです。 種子原人さんへ、夜中の眠い時間にお返事ありがとうございました。赤米って美味しくないんですか? でも、食べてみないとわからないですよね『美味しくない』ってことがね。 古代には、美味しかったんでしょうね。私も味見してみますね。どれ位美味しくないか・・・ね。 ほんで、緑米と黒米(古代の餅米)で、作ったお餅も食べてみますね。 夢でも参加していただけるなんて、嬉しいです。私の作った弥生土器がきれいに焼けるように、祈っていてくださいね。※ 厚かましかったですかね。 【写真】赤米(古代米)です。 きっと持統天皇は「美味しいですわね!」って食べていたことでしょう。 もちろん、私はよう作らんのですよ。 もし、作ったとしても食べられるようにするまでの手順が・・・ね? 菅野さんのように、自分の家で乾燥〜籾摺り〜白米までできるんだったらいいのですけどね。 2009/09/30 08:09:山さくら:URL
|
▼100advertising▼ranking
|
|
(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
|
|
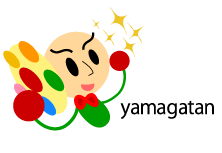
青年達が農業労働者の方に惹かれるのは根拠のないことではないよな。
前回のブログの末尾に書いたけれど、
農家になること、それを続けること、村の付き合い・・などを考えれば
手っ取り早く勤め人になったほうが・・と考えるのも仕方がないともいえる。
青年達は農家になることを求めているのではなく、今よりももっと土や生命体とつながることをもとめているのだろうし、その方向を農的生活へのパーセンテージを高めることにおいているのだろうから。
この動機自体は歓迎すべきことで、否定されることではないべね。
ここでロシアのダーチャを思い起こすよ。
「ロシアは今も荒れ模様」(米原マリ著)で知ったのだけど
ソ連からロシアに変わる動乱の時期、経済破綻の時期にあっても
国民の食糧生活は安定していた。その訳はダーチャにあったと書かれている。
青年達の農への流れと日本型ダーチャの構築とを
つなげられないだろうか。
青年達に限らず、国民全体の農的生活のパーセンテージを高めていく方向にだよ。
農家も、生産法人も、半農半Xも、ダーチャも・・・
混在する転換期の日本農業・・・。
いいんじゃないだろうか。